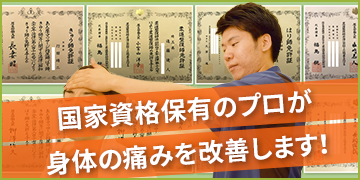ブログ
HOME > ブログ
HOME > ブログ

過敏性腸症候群とは??
特に疾患を抱えているわけでもないのに腹痛や腹部膨隆感を伴う便通異常を起こす病気です。
日本人には割合多い疾患の1つです。
便通異常として、下痢と便秘が続いてしまう症状があります。これは、腸管の運動が異常に亢進したり、刺激に対する反応が過敏になっているためと考えられています。
心因性や自律神経失調が原因であることが多く、心因性としては不安や緊張、ストレスや性格の影響が大きいといわれております。ストレスにより不安状態に陥ると、腸の収縮運動が激しくなり、また痛みを感じやすくなります(知覚過敏)。
この状態が強いことが過敏性腸症候群の特徴になります。
病院ではこれらの診断方法として、ローマⅢ基準というものがあります。
・最近3カ月の間に、月に3日以上にわたってお腹の痛みや不快感が繰り返しおこり、
下記の二項目以上の特徴を示したら過敏性腸症候群の疑いがあります。
1)排便により腹痛、不快感がやわらぐ
2)症状とともに排便の回数が変わる(増減する)
3)症状とともに便の形が変わる(柔らかく、硬くなる)
過敏性腸症候群であるとわかったら
ヨーグルトやみそ、納豆などの発酵食品は症状の軽減に有効なので、是非やってみてください。
ここで当院ふどうまえ駅前整骨院では、どんな事が出来るの?
当院では、背骨・首の骨・骨盤を矯正する「モルフォセラピー」という施術法を行っております。
モルフォセラピーでは骨のズレによって様々な症状をだしていると考えています。
また、ツボを使った施術でレインボー療法を組み合わせることにより内部にアプローチすることが出来ます。
過敏性腸症候群の症状に、腸管の運動の異常亢進や感覚が過敏になることがあります。
腸管を支配している神経は、自律神経の中でも副交感神経が支配をしています。
この副交感神経の枝を出している個所の背骨や骨盤のズレが大きく、うまく交感神経と副交感神経の伝達交換が出来ないために症状がでてきます。
骨のズレによる影響を取り除くのに、モルフォセラピーはかなり有効な施術法です。
お体の状態や現在の治療状況、生活背景をお伺いし、1人1人にあった施術をさせていただきます。
過敏性腸症候群に悩まれている方へふどうまえ駅前整骨院で良くしませんか?
当院への予約は03-6303-9193 担当 高橋 やとみまで
2020.2.28
ストレートネックとは正常な頸椎のカーブが何らかの原因によりストレートになってしまうことです。
ストレートネックになると何がよくないのか?
ストレートネックになると本来の首の機能が失われ、頭を支えることが骨でできないため肩まわりの筋肉や腰の筋肉を使うことになり
肩こりや腰痛、頭痛になることもあるので良くありませんね。
また、神経も血管も筋肉の近くを通っているため影響を受けます。要注意です。
自分がストレートネックかどうか?
簡易検査として壁に身体をつけ頭が壁から浮いてしまうかどうかです。
浮いてしまうとストレートネックの可能性があります。詳しくは専門の所で診てもらいましょう。

当院ではストレートネックの施術が出来ます。
頸椎のカーブを整えることにより首の痛みや肩こりや腰痛を良くすることが出来ます。
2020.2.18
眼精疲労とは
眼精疲労は目の循環機能が悪くなることで起こり段々と症状が強くなり慢性化し
続いて他の部分にも影響がでてきます。肩こりや頭痛、姿勢不良により腰痛がでてきます。
日ごろの姿勢を見直すことも眼精疲労を解消するためには必要ですし
適度な運動やストレッチは筋肉の活動を促し血行を良くします。
お風呂で内部の循環を良くすることもお忘れなく。
それでも仕事等で負担のかかってしまうと上記の方法では間に合わないことも
当院へお任せ下さい↓↓
良くするには
循環機能を良くすること。具体的には頸椎のズレを矯正することで血液の循環を良くすることが効果的です。
C1C2C3を綺麗に整えることを中心に周りの筋肉の緊張を緩和させ姿勢良くしていきます。
同時にホットパックでジンワリ温めるとさらにグット!!
疲労はその日のうちに解決しておきたいものですね。
局所の治療だけでなく、全身を把握し調整をするため
期間を要してご自身の大切な身体を調整できます。
モルフォセラピーや構造医学といった様々な治療法で対処いたします。
一人で悩まず一緒に解決していきましょう!
身体がお困りの方は、お早目にどうぞ→03-6303-9193
ゆがみとケガ、事故に強いふどうまえ駅前整骨院
不動前駅より徒歩0分 目黒駅より徒歩13分 五反田駅より徒歩18分
2020.2.13
・手根管症候群
手根管症候群とは正中神経が手首で圧迫され症状をだす病気です。
正中神経(せいちゅうしんけい)は手の感覚,親指のふくらみの筋肉を支配する神経です。
正中神経は指を動かす9本の腱と一緒に,手くびの部分で手根管(しゅこんかん)という狭い管(くだ)を通過します。
手根管の屋根にあたる横手根靱帯が厚くなったり、腱の炎症(腱鞘炎)が起こることで、正中神経が圧迫されるのが病気の原因です。
40代以降に多く,女性と男性の比は1対2~1対5と言われ、女性に多い病気です。日常生活や仕事で手を良く使う人がなりやすい傾向があります。
関節リウマチ、長期間の血液透析、手首の骨折、妊娠が原因になることがあります。
症状
手のひらから、親指、人差し指、真中指、薬指半分のしびれが起こります。しびれは朝方に強かったり、自転車や車の運転、編物など手を使うことで強くなりやすく、手を振ると少し楽になるのが特徴です。
中年の女性に多く、手の甲はしびれず、手首より手前がしびれることはありません。また薬指の親指側半分しかしびれないので、しびれる場所からある程度診断することができます。
症状が進むと、親指付け根の筋肉が痩せてきたり、親指の力がおちるため、物を落としやすくなってしまいます。
・治療
消炎鎮痛剤やビタミンB12などの飲み薬、塗布薬、運動や仕事の軽減などやシーネ固定などの局所の安静、腱鞘炎を治めるための手根管内腱鞘内注射などの保存的療法が行われます。
難治性のものや母指球筋のやせたもの、腫瘤のあるものなどは手術が必要になります。手術には、以前は手掌から前腕にかけての大きな皮膚切開を用いた手術を行っていたが、現在はその必要性は低く、内視鏡を用いた鏡視下手根管開放術や小皮切による直視下手根管開放術が行われている。
当院でも保存療法をしておりますが、圧迫を取り除くように手首の骨の矯正をし改善を目指します。
急な手のシビレや病院、整形外科に行ったがなかなか症状が変わらないかたなど気軽にご相談からでも受付ます。
お困りのかたは→03-6303-9193 ふどうまえ駅前整骨院
2020.1.29

顎関節症(ガクカンセツショウ)の症状は・・・
あごの関節に不具合が生じ口を開けた時に痛みを生じたり音が鳴ったり、ズレる感じあったり、大きく開けられないことが起こります。
顎関節症のなりやすさは以下のチェックを確認してください
□歯を食いしばる癖がある
□歯ぎしりをする
□うつぶせで寝る習慣がある
□歯並びやかみ合わせがよくない
□ものを食べるとき左右どちらかだけで噛んでいる
□奥歯が抜けたまま放置している
①あごを動かす筋肉の痛み(咀嚼筋痛障害)
②顎関節の痛みを主な症状とするもの(顎関節痛障害)
③顎関節の中の関節円板のずれが生じるもの(顎関節円板障害)
④顎関節を構成する骨に変化が生じるもの(変形性顎関節症)が含まれています。
顎関節は咀嚼する。ものを噛む際に必要なため一日たりとも使わない日はほぼありませんよね。
痛みが原因でかばっていると余計に状況が悪化し症状が強くなることも珍しくありません。
早期解決が好ましいです。(肩こりの原因にもなります)
当院でどうやって解決していくのか?
顎関節のズレや筋肉の状態、運動時の動きを検査し本来の顎の位置に調整する手技と周りの筋肉の緊張を整えていきます。
顎を支配する神経にもアプローチをかけ早期回復を目指します。モルフォセラピーや運動療法
顎関節は早期に対処しないと一日で動かさない日はほぼないですよね。
ゆがんだ状態で使っていると戻せなくなりますので気付いた時にはすぐに調整しましょう。
2019.12.13
慢性疲労症候群は、身体を動かせないほどの疲労が6か月以上の長期間にわたって続き、日常生活に支障をきたすほどになる病気です。
Chronic Fatigue Syndrome「CFS」
かぜに似た症状がいつまでも長引くのと同じような状態で発症することが多い病気です。休んでいても改善しなかったり、摂食障害や不眠などを伴っている場合は要注意です。こうした場合で、血液検査も含む全身の検査(ホルモンの異常、内臓や脳、神経系の検査など)をいくら行なっても異常が見つからないとき、慢性疲労症候群が疑われます。
こんな症状は注意です。
休養や睡眠をとっても回復しないことと6カ月以上の長期にわたって日常生活に支障をきたすことです。
厚生労働省の診断基準は
・症状基準(以下の症状が6ヵ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)
・微熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒、咽頭痛、頚部あるいは腋窩リンパ節の腫脹
・原因不明の筋力低下、筋肉痛ないし不快感、軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感
・頭痛、腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛
・精神神経症状(いずれか1つ以上=光過敏、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、混乱、思考力低下、集中力低下、抑うつ)
・睡眠障害(過眠、不眠)、発症時に主たる症状が数時間から数日の間に出現身体所見基準(少なくとも1ヵ月以上の間隔をおいて2回以上医師が確認)
・微熱、非浸出性咽頭炎、リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)または圧痛です。
当院では、背骨・骨盤を中心に矯正をする、モルフォセラピーを専門に施術をしています。
背骨・骨盤のズレを整え、自律神経の働きを正常に戻し本来の身体の調整をし回復力を促します。
一人で悩まず一緒に解決していきましょう!
身体がお困りの方は、お早目にどうぞ→03-6303-9193
ゆがみとケガ、事故に強いふどうまえ駅前整骨院
不動前駅より徒歩0分 目黒駅より徒歩13分 五反田駅より徒歩18分
2019.11.26
皆さんこんにちは。
今年のプロ野球の日本一が決まりもう今年もわずかになりました。
プレミヤ12でも日本が世界一になりテンションがあがっていました弥富です。
今回は野球をしている、していた方なら一度は耳にしたことがある「野球肘」について書いていきたいと思います。
野球肘とは・・・
野球肘は名前の通り野球の投球動作で肘に負荷がかかり過ぎて起こる、小中学生に多いスポーツ障害の一種です。
成長期に骨が障害されるため、肘の痛みのみならず将来に禍根(かこん)を残す骨変形をも合併します。
現在、甲子園に出場する投手は肘のメディカルチェックが義務づけられ、レントゲン検査など障害の程度によっては出場禁止にもなることもあります。
原因
ボールを投げるときには肘には大きな力が加わります。
速い球を投げたり、肘下がり、手投げと言われるような悪いフォームで投げたりすると、1回1回の投球で肘にかかる負担が大きくなります。また球数が多くなると負担が増えます。
1回の負荷があまりにも大きければ骨や靭帯が破損して「怪我」が起こります。球数が増えて肘の負担が大きくなれば「故障」が起こります。
内側側副靭帯損傷(内側型野球肘)と離脱性骨軟骨炎(外側型野球肘)
・内側側副靭帯損傷(内側型野球肘)
内側型野球肘の方が頻度が圧倒的に高く、特に野球少年が多く罹患します。
投球動作によって肘の内側に離れようとする力が繰り返しかかることによって発生し、成長が終わった高校生以降では骨と骨をつなぐ靭帯自体が損傷され、少年期には靭帯が付着している成長軟骨付近の骨成分が傷みます。
しかし、重症となることは少なく、多くの場合は安静にすることで軽快します。
・離脱性骨軟骨炎(外側型野球肘)
外側型野球肘は、肘の上の上腕骨と下の橈骨(とうこつ)が、投球動作でぶつかる力がかかり続けることで、雨だれがコンクリートをへこますがごとく、骨の表面にある関節軟骨を傷つけていきます。
これが進行して発症し、発生頻度は低いものの、どんどん悪化する場合は手術が必要となることもあります。
主な治療
主原因であるオーバースローのピッチング動作の休止を徹底します。
また、投球後のアイシングを徹底します。骨変化が認められる場合は、3ヵ月以上のスローイング動作の休止が必要です。
骨に変化をきたしている場合は、最低1-3年ぐらいのフォローアップが必要です。
遊離骨片によって肘がロッキングしている場合は、骨片摘出手術が必要となります。
ただしランニングやバッティングは可能であり、ポジション変更の等で対処することがほとんどです。
肩や肘の痛みで悩んでいる方、病院や整形外科に行きなかなか症状が変わらないかたなど気軽にご相談からでも受付ます。
お困りのかたは→03-6303-9193 ふどうまえ駅前整骨院
2019.11.22
皆さんこんにちは!
急な寒さについていけずに風邪をひいてしまった弥富です。
今日はあまり聞きなれない胸郭出口症候群について書いていこうと思います。
胸郭出口症候群とは?
胸郭出口症候群とは簡単にいうと肩から手にかけて痺れをだしてしまうものです。
胸部には心臓や肺という大切な臓器が存在し、これを守るように胸骨・肋骨と脊椎骨(せきついこつ)によってぐるりと囲まれています。
この骨格および周囲の筋肉や皮膚によって胸壁ができあがっています。
この胸壁と、胸部・腹部とを分ける筋肉の膜である横隔膜に仕切られた入れものが胸郭です。
上肢やその付け根の肩甲帯の運動や感覚を支配する腕神経叢と鎖骨下動脈は以下の部分を走行します。
・前斜角筋と中斜角筋の間
・鎖骨と第1肋骨の間の肋鎖間隙
・小胸筋の肩甲骨烏口突起停止部の後方
それぞれの部位で絞めつけられたり、圧迫されたりする可能性があります。
その絞扼(こうやく)部位によって、斜角筋症候群、肋鎖症候群、小胸筋症候群(過外転症候群)と呼ばれますが、総称して胸郭出口症候群と言います。
胸郭出口症候群は神経障害と血流障害に基づく上肢痛、上肢の痺れ、頚肩腕痛を生じる疾患の一つです。
診断
胸郭出口症候群は神経伝導検査、筋電図検査、血管造影検査、エデンテスト、ライトテスト、アレンテスト、アドソンテストと言った徒手検査でも判断することは出来ます。
しかし、これらのどの検査でも、胸郭出口症候群の診断を確定することや、その可能性を否定することはできません。
予防と治療
症状を悪化させる上肢を挙上した位置での仕事や、重量物を持ち上げるような運動や労働、リュックサックで重いものを担ぐようなことを避けさせます。
症状が軽いときは、上肢やつけ根の肩甲帯を吊り上げている僧帽筋や肩甲挙筋の強化運動訓練を行なわせ、安静時も肩を少しすくめたような肢位をとらせます。
肩甲帯が下がる姿勢が悪い症例には肩甲帯を挙上させる装具が用いられます。
病院では消炎鎮痛剤、血流改善剤やビタミンB1などの投与も行なわれます。
当院では原因となる神経や骨格の部分にアプローチして神経の通り道を確保し、しびれや痛みを軽減します。
手や肩のしびれ、痛みで悩んでいる方、病院や整形外科に行きなかなか症状が変わらないかたなど気軽にご相談からでも受付ます。
お困りのかたは→03-6303-9193 ふどうまえ駅前整骨院
2019.11.21

①姿勢によるゆがみ
・長時間のデスクワークや、足を組んだりなどの姿勢 ・運動不足による、血行不良 ・間違った体の使い方 など
②電磁波による筋肉の過度な緊張
・パソコンやスマホ、様々な電気機器から出ている電磁波が、筋肉を緊張させて、体をゆがませると言われています。
人間の体は電気が帯びています。プラスイオンとマイナスイオンです。体がプラスイオンに片寄ると、緊張が強くなり、ゆがんだり、血行不良になります。
マイナスイオンに片寄ると、リラックスができ、筋肉も柔らかい状態になります。
もちろんバランスが大切なのですが、現代では、プラスイオンに片寄っている人が多いようです。静電気が起きやすい状態はプラスイオン優位です。
③食品添加物などによる、筋肉の過度な緊張
・最近では食品に入っている、様々な添加物による筋肉の緊張も報告されています。メカニズムとしては、添加物→神経が過剰に興奮→筋肉を固くするという流れです。
④内臓の疲れによる体のゆがみ、血行不良
東洋医学では、「体の不調は内臓からのサイン」と言われています。腰が痛くても、睡眠の質が下がっていても、内臓の働きを高めてあげると改善していくという考え方です。
⑤自律神経(緊張とリラックス)のバランスの悪さ
現代では仕事のストレスや運動不足などにより、体の緊張時間が長くなっていると言われています。それがクセになり、寝ているときも緊張状態が続き、血流が悪くなっているため、睡眠の質が下がり、回復しなくなります。(モルセラより引用)
不眠症以外にも様々な病気があり、多くの人々が睡眠の問題を抱えていることがわかってきました。
夜の睡眠が障害されると、眠気やだるさ、集中力低下など日中にも症状が出現します。
睡眠障害から腰痛や肩こりや頭痛、筋肉が十分に休めていない状態ではそこから他の症状に波及することはイメージがつきやすいのではないでしょうか?
当院では根本的な睡眠を障害することを解決するゆがみを補正し血液の流れを正常にしホルモンバランスを良くすることを目指します。
2019.11.9
ランナーの膝におこりうること
走っていると機械的な摩擦が身体の中で起こり炎症します。そこは膝関節近くで靭帯と骨がぶつかることで起こります。
俗にランナーに多いことからランナー膝と呼ばれ長距離走る方に多いです。(腸脛靭帯炎)
自覚症状としては、ランニングによる膝の外側の疼痛です。
腸脛靭帯炎が発生しやすいスポーツには、陸上の長距離競技、自転車競技などが挙げられます。
大腿骨外顆周辺に限って圧痛が存在し、腸脛靱帯は明らかに緊張が増し、靱帯の走行に沿って疼痛が放散する場合があります。
初期はランニング後に痛みが発生しますが、休むと消失します。しかし、ランニングを続けていると次第に疼痛は増強して、簡単に消失しなくなってきます。
当院では
関節にかかる負担を軽減するモルフォセラピーや同時に身体の機能を保持するインナーを合わせておこうことにより
負担の軽減を目的として行います。
炎症を抑える冷却や固定、テーピング補助や電療の他に関節や筋肉、神経を良くし早期改善
走ることで筋力量がアップしたり代謝が良くなり健康には必要です。また、筋力がアップすることで関節を守ることにつながるため将来杖や車いすに乗らないためにも
ケガは早期に治しましょう。
2019.11.6

クレジットーカードでのお支払いは、自費診療と物販製品のみご利用可能です。
保険診療の一部負担金にはご利用いただけません。