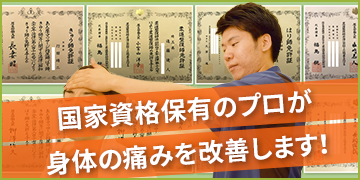ブログ
HOME > ブログ
HOME > ブログ
みなさんこんにちは!
9月になり秋に近づいてくる時期ですが、まだまだ残暑が続きますね・・・。
体調を崩したりはしていないでしょうか?
又、夏バテしている方もいるかもしれません。
夏バテを吹き飛ばすためにもしっかり栄養を摂るようにしていきましょう!!
今月も旬な食材をご紹介していきます!!
9月の旬な食材は《シイタケ・オクラ・かぼす・サンマ・昆布》などがあります!
その中でも【オクラ・かぼす・昆布】を紹介致します。
☆オクラ

オクラにはネバネバした特徴のある食物繊維があります。この食物繊維はガラクタン・アラバン・ペクチンという成分です。
この食物繊維はネバネバした特徴です。
・ペクチンは整腸作用を促し便秘や下痢を予防して大腸がんのリスクを減らす効果が期待でき、コレステロールを排出させる作用もあります。
・βカロテンも含まれていて、βカロテンは体内でビタミンAに変換され鼻や喉の粘膜・皮膚の健康を保ったり抵抗力を強くする働きがあります。免疫力の維持に役立つ栄養素です。
・葉酸も含まれていて体内で赤血球の生産を助ける働きをしている為、葉酸が不足すると貧血の一因になることがあります。
又、細胞の生産や再生を助ける働きもある為欠かさずに摂っていきましょう!!
特に胎児の発育においては重要なので、妊婦さんは積極的に摂るようにしましょう!!
・ミネラル(カリウム・カルシウム)カリウムは体内の塩分を排出させる働きがある為、高血圧予防に効果的です。
カルシウムは骨や歯の形成に重要な栄養素です。
☆かぼす

かぼすはミカン科の柑橘類です。皮が青い間に収穫され熟すと黄色い色になります。
(かぼすに似たすだちとの違いは、かぼすはテニスボール程の大きさ。すだちはゴルフボール程の大きさです。)
かぼすには多くのビタミン類が含まれますが、その中でもビタミンCが豊富で美肌作用・免疫力アップ・老化予防に効果があります。
・ビタミンCは果物や野菜に含まれる水溶性の栄養素でコラーゲン合成を促進したり、シミやそばかすの元であるメラニン色素を抑える機能を持っています。さらに抗酸化作用もあり活性酸素の増加を抑える事で老化や生活習慣病を予防します。鉄の吸収を促して、身体の免疫力を強めてくれるので風邪予防にも効果的です。
・コレステロールを低下させる
コレステロールが増えすぎると動脈硬化が進行し、心筋梗塞・脳梗塞などの病気を発症しやすくなります。
かぼすに含まれるフラボノイド系の栄養素にコレステロールを低下させる機能があると期待されています。
・クエン酸
疲労回復が望めるクエン酸が含まれています。クエン酸は梅やレモンなどにも含まれる酸味成分の一種です。エネルギー代謝を活発にして疲れの回復をスムーズにすると考えられています。
又、クエン酸の酸味には唾液や胃液の分泌を促し食欲を増進させる効果もあります。
・カリウム
カリウムは必須ミネラルの一種でナトリウムを体外に排出するのを助け、血圧を低下させる効果があるので高血圧を改善するのに効果的です。
☆昆布

昆布には独特の粘り成分があり、『アルギン酸』・『フコイダン』の成分が粘り気を出します。
・ヨウ素
ヨウ素は甲状腺ホルモンの成分になるミネラルで、エネルギー代謝を促進する働きや身体の成長を促進する効果があります。特に成長期の子供には欠かせない栄養素です。ただし過剰摂取は甲状腺機能を低下させてしまうので注意が必要です。
・食物繊維
水溶性食物繊維の一種であるアルギン酸やフコイダンが豊富に含まれています。
水溶性食物繊維は腸内環境を整える効果や血糖値の急激な上昇を抑える事やコレステロールの吸収を抑制させる効果が期待できます。
・カルシウム
骨や歯を作るのに欠かせないミネラルです。ビタミンDと一緒に摂る事で吸収率が良くなります。
しっかり栄養があるものを摂取して健康な身体を作っていきましょう!!
2022.9.1
みなさんこんにちは!
8月に入り暑い日々が続いていますが、皆さんはどうお過ごしですか?
暑い日々が続くとついつい冷たい飲み物や食べ物を摂りがちですが、夏ではエアコンの冷房で身体が冷えている可能性があるので温かい食べ物を食べるように心がけて下さい!!
8月は山の日がありますね!山の日は祝日になりますので、近くの山に行ってハイキングなんてのも良いと思います。
ハイキングをするためには健康な身体作りをしなくてはいけないので、旬な食材を摂って栄養をつけるようにしましょう!!
8月の旬な食材を紹介していきます。
【青トウガラシ・きゅうり・モロヘイヤ・メロン・ブドウ・鮎・カジキマグロ・昆布】などがあります!!
その中でも≪モロヘイヤ・ブドウ・カジキマグロ≫をご紹介します!
☆モロヘイヤ


・モロヘイヤは王様の野菜と呼ばれていて、βカロテンが豊富に含まれています。
βカロテンは体内でビタミンAに変換される栄養素で皮膚や粘膜の健康を保つ働きをもっています。
その他に細胞を傷つける原因のひとつである活性酸素を防ぐ抗酸化作用もある為、若々しい肌を保つ為にも重要な栄養素です!
人参よりもモロヘイヤの方がβカロテンが多く含んでいます。
・ビタミンCも多く含んでいて美肌を保つのに欠かせないコラーゲン生成にも必要な栄養素です。又、ビタミンCには植物性の鉄分吸収を助け、免疫機能が適切に働くようにサポートしてくれます。
・ビタミンEも含まれていて、ビタミンEは強い抗酸化作用をもっており細胞の酸化(老化)を防いでくれます。
さらに血管を拡張することで血液の凝固を防いだり赤血球の破壊を防ぐ役割もあります。
モロヘイヤのビタミンE量は他の緑黄色野菜の3倍以上含まれていて、アンチエイジングや血管の健康を保たせます。
・葉酸も含まれていて、葉酸には赤血球を産生したり発育に重要なDNA・RNAの産生を助ける働きがあります。
※葉酸を多く含まれる食材の『ほうれん草』よりも【モロヘイヤ】の方が葉酸を多く含まれています!!
モロヘイヤは水溶性食物繊維の為、茹でる際には短時間の方が良くオクラと一緒に摂る事で水溶性食物繊維がたくさん摂取できます。
お腹が張っている感がある便秘気味の方にはオススメです!
☆ブドウ
ブドウにはポリフェノール・ブドウ糖・カリウム・ビタミンB群・有機酸が含まれます。
・ポリフェノールは眼精疲労や動脈硬化を予防する効果が期待できます。
ポリフェノールはブドウの皮に多く含まれているので、皮ごと食べる事をオススメします。
皮が苦手という方は無理をしないで大丈夫です。
・ブドウ糖は腸で吸収しやすい糖質が多く含まれている為、疲労回復の効果が期待できます。
消化酵素をあまり使わずに腸で素早く吸収される為、エネルギー補給に適しています。
・カリウムはむくみ予防を期待できます。
むくみは体内の塩分量が多い時に塩分量を緩和させるために身体が体内に水分を蓄える事により起こります。
カリウムは塩分量を調整する働きがあり、体内の塩分を減らす利尿作用でむくみ予防になります。
・ビタミンB群はエネルギー代謝を助け粘膜の再生・免疫機能の維持・貧血・疲労感を軽減する作用があります。
・有機酸は抗酸化・抗菌性が期待され疲労回復・整腸作用があります。
☆カジキマグロ

カジキマグロはマグロの仲間ではなく、スズキ目の一種でその中でもメカジキ科とマカジキ科のカジキを指します!
カジキマグロは脂肪分が少なく、良質なタンパク質を豊富に含まれています。
タンパク質は体力アップをさせる効果があります。又免疫細胞の原料としても働きます。
ビタミンB群も多く含まれていて、代謝をサポートしてくれる効能があります。
さらに良質なDHA・EPAを含む為、コレステロール値の低下に作用します。
旬な食材を摂取して夏バテ知らずの身体作りをしていきましょう!!
2022.8.1
みなさんこんにちは!
もう7月に入ってしまいましたね。
みなさんは体調を崩したりしていないでしょうか?
暑くなってくると良い栄養を取らずについ冷たい食べ物を摂取しがちですが、エアコンの冷えもある為、なるべく暖かい食べ物を摂るようにして下さい!!
今月も旬な食材をご紹介していきます!!
7月の旬な食材は【いんげん・枝豆・新ショウガ・冬瓜・梅・パイナップル・桃・アナゴ・うなぎ・ウニ】などがあります!
その中でも『枝豆・ウナギ』をご紹介していきます!
☆枝豆
![枝豆[11012019332]の写真素材・イラスト素材|アマナイメージズ](https://static.amanaimages.com/imgroom/rf_preview640/11012/11012019332.jpg)
枝豆は熟す前に収穫された大豆です。つまり枝豆と大豆はもともと同じ物でまだ色が青いうちに収穫されたものを枝豆。
完熟して茶色くなってから収穫されたものが大豆です。
実際には枝豆として食べるのに適した枝豆専用の品種。大豆として適した大豆専用の品種に分けられています。
・枝豆の栄養は《畑の肉》と呼ばれる大豆と同様にタンパク質がたっぷり含まれています!
筋肉・骨などの身体作りや体内のホルモン・酵素などの生成を担うタンパク質は人体に欠かす事が出来ない重要な栄養素です!!
枝豆に含まれる植物性タンパク質の特徴は肉や魚などの動物性タンパク質に比べて脂肪が少ない事です。
高タンパクなのにヘルシーなので、筋トレの効果を引き出す食材としても知られています。
・イソフラボンも含まれていて、イソフラボンは枝豆の胚芽部分に多く含まれているポリフェノールの一種です。
体内で女性ホルモンに似た働きをして肌のハリ・ツヤを保ったり・シワやたるみを改善したりする美肌効果を発揮してくれます。
ホルモンバランスの乱れによる女性の心身の不調や更年期障害の症状を和らげる効果も期待できます。
・肝臓の機能を司るアミノ酸・メチオニン含有量も枝豆の特徴な栄養素です。
肝臓でアルコールが分解される時に欠かせない《メチオニン》が多く含まれていて二日酔い対策にも有効です。
・体内で糖質や脂質を分解してエネルギーを作り出す際にビタミンB1・B2が必要ですが、ビタミンB1・B2も多く含まれています。ビタミンB1・B2は疲労回復・夏バテ防止に有効です。又、ビタミンCも多く含まれる為、免疫力アップにも効果的です。
※ビタミンB1・B2・Cはメチオニンとともにアルコール分解を助ける役割もしています。
・枝豆にはカリウムも含まれ、カリウムは細胞内液の浸透圧を調節するミネラルとなります。余計なナトリウム(塩分)を体外に排出するので血圧を下げて高血圧を予防する効果があります。又、カリウムはむくみの解消や筋肉の収縮を正常に保つのにも有効な成分です。
枝豆と大豆には栄養素の違いがあり、枝豆が優秀な栄養素はビタミンC・βカロテン・葉酸が含まれている事です。
これらは大豆にはない成分なので、枝豆を食べると良い効果がありますね!!
☆ウナギ
![うな重[11020002688]の写真素材・イラスト素材|アマナイメージズ](https://static.amanaimages.com/imgroom/rf_preview640/11020/11020002688.jpg)
ウナギにはDHA・EPAといった不飽和脂肪酸が豊富です。
DHAは脳の発達促進・視力低下予防・動脈硬化の予防改善
EPAは高血圧予防や炎症を抑える働きが期待できます。
・レチノールも含まれ、レチノールは目や粘膜の健康を保ちます。ビタミンAの主成分であるレチノールは脂溶性ビタミンに分類され、目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を高める効果が期待できます!!
・ウナギは骨や歯のの構成成分になるカルシウムも豊富です。
カルシウムは身体の中に最も多く存在するミネラルでストレスを和らげたり、血が固まるのをサポートする働きも期待できます。
・ウナギには疲労回復に効果があるビタミンB1も豊富に含まれ、魚介類ではトップクラスに入ります。
・筋肉の構成成分となるタンパク質も含まれます。ウナギのタンパク質は動物性タンパク質で身体を作る構成成分だけではなく、身体の機能を調節する働きもあります。
夏バテになる前にしっかり栄養を摂って健康な身体作りを心がけて、夏を楽しみましょう!!
2022.7.1
こんにちは!
6月といえば梅雨入りの季節となりますが、体調を崩されていないでしょうか?
梅雨に入ると低気圧の影響で、頭痛や古傷が痛みやすい方が多く感じます。
痛みが出る前に身体のメンテナンスをしていきましょう!!
又、栄養をしっかり摂り、痛みが出ない身体作りをしていきましょう!!
今月も旬な食材をご紹介していきます。
6月の旬な食材は【さやえんどう・そら豆・梅・サクランボ・びわ・イサキ・ハモ・もずく】
その中でも《そら豆・さやえんどう・もずく》をご紹介いたします!
☆そら豆
![そら豆 写真素材 [ 6344818 ] - フォトライブラリー photolibrary](https://www.photolibrary.jp/mhd2/img762/450-20200402161856156119.jpg)
そら豆にはカリウムが多く含まれています。カリウムは塩分(ナトリウム)の排出作用があります。
塩分の摂りすぎが気になる時は積極的に摂るようにしましょう。
又、ビタミンB1も含まれていてビタミンB1は主に糖質の代謝につかわれます。
ブドウ糖がエネルギー源になる時もビタミンB1の働きが重要になってきます。
それ以外にも葉酸、ビタミンC、食物繊維も含まれています。
葉酸は細胞の生産や再生を助ける働きがあり身体の発育や成長に関わってきます。
さらに葉酸はビタミンB12と協力し設計の生産を助ける働きがあります。魚介類や海苔などのビタミンB12を含む食品と合わせて摂ると良いです!
ビタミンCにはコラーゲン生成に重要な栄養素です。コラーゲンは骨や腱のほかに血管の健康にも関わっており、ビタミンCが不足すると血管がもろくなり出血しやすくなります。
食物繊維は水に溶ける水溶性と溶けない不溶性があります。そら豆に含まれる食物繊維は不溶性食物繊維です。不溶性食物繊維には腸を刺激してぜんどう運動活発にし、排便をスムーズにしてくれる作用があります!
又、豆の食物繊維は茹でると増えるという性質があります。これは、でんぷんの一部が加熱される過程で☆難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)☆に変化する為と言われています。
☆さやえんどう

さやえんどうにはβカロテン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンK、リジンが含まれています。
・βカロテンは体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。ビタミンAは目の機能や皮膚や粘膜の健康を保つ為に必要で粘膜のダメージを回復させる効果や免疫力を高める効果があります。
又、肌荒れ予防にも効果が期待できます。ビタミンAに変換されなかったβカロテンは抗酸化物質として働き、動脈硬化やガンなどの生活習慣病の予防・老化防止に効果が期待できます。
・ビタミンCはコラーゲン合成に関わるビタミンでストレスから身体を守る働きをします。
活性酸素を消去する抗酸化作用があり、動脈硬化予防にも効果があります。さらには、皮膚のシミやシワを防ぎ傷や炎症の治りを良くする効果があります。粘膜を強くして健康に保つ効果もあることから風邪予防の効果も期待できます。
・ビタミンB1は糖質のエネルギー代謝に関わっており、疲労回復を助ける効果があります。
又、脳と神経を正常に保つ働きもしています。水に溶けやすいので、煮汁も一緒に摂れる料理にすると効果的に摂取できます。
・ビタミンKはビタミンDと共にカルシウムの吸収を良くする働きがあります。骨からカルシウムが溶けて血液に流れ出るのを防ぐ役割があり骨形成に重要な働きをしています。
・リジンはさやえんどうの豆の部分に含まれているアミノ酸の一種です!
身体の組織の修復を促す働きや肌の組織を整える事や骨・血管を丈夫にするなどの効果が期待できます。
☆もずく
![もずく酢 沖縄もずく 写真素材 [ 6515191 ] - フォトライブラリー photolibrary](https://www.photolibrary.jp/mhd1/img793/450-20200908005014263017.jpg)
もずくは昆布やワカメなどの褐藻類です。
カルシウム・マグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれており、食物繊維も豊富です。また、葉酸やカルシウム・βカロテン・フコイダンも含まれています。
マグネシウムは歯や骨を作る為に必要なミネラルです。さらにカルシウムと協力して筋肉の働きを調整する役割もあります。
フコイダンはもずくのぬめりの元になっている成分で悪玉コレステロールの排出を促す働きや糖質の吸収を抑えて血糖値の上昇を抑える働きがあります!
みなさんも旬な食材を摂って健康な身体作りをしていきましょう!!
2022.6.1

みなさんこんにちは!
GWはどうお過ごしでしたでしょうか??
今年は久しぶりに何も規制されてない長期休みで羽を伸ばせたことと思います。
さて今回、一度は聞いたことがあるであろう「四十肩、五十肩」という方の痛みについて書いていきたいと思います。
四十肩、五十肩とは?
40代、50代に起こりやすい、肩の強烈な痛みを通称「四十肩」「五十肩」と呼びます。
四十肩、五十肩は、その名の通り40代で症状が出れば四十肩、50代で症状が出れば五十肩と呼んでおり、それぞれに違いはありません。
四十肩・五十肩は加齢によるものが多く、特徴として肩の可動域が極端に下がり手を挙げるのが困難になります。そのため、洗濯物が干しづらくなった、肩よりも上のものが取りづらくなった、背中のファスナーがあげられないなどの症状が現れます。
よく肩こりと混同されてしまいがちですが、肩こりは筋肉の緊張などから起こるもので、四十肩、五十肩とは全く違うものになります。
肩の痛みが出て、徐々に痛みが強くなる、痛みで肩を動かせない、腕が上がらないなど似たような症状が出た時は早めに対処しましょう。
なぜ起こる?
四十肩・五十肩は、肩関節周辺の様々な組織が炎症を起こしている状態ですが、良く言われるのが肩の関節にある「腱板」という組織が炎症を引き起こし「関節包」に広がる事で起こります。
老化によるものと言われますが実際のところ原因は、まだ明確に分かっていません。
症状
四十肩・五十肩の病状は、「急性期」・「慢性期」・「融解期」と3段階に分かれて進行します。
・急性期
発症してからしばらくは、強い炎症が起きている時期です。
数週間~数ヶ月間で、肩を中心に腕全体が痛みます。安静時も痛みがでたり、動かすのも強い痛みがでます。
日常生活、特に洋服を脱ぐときなど腕を大きく動かすシーンで激しい痛みを訴えます。
寝返りの際も痛みが出るため、生活に支障をきたす場合もあります。
・慢性期
安静時の痛みがだいぶ和らぎ、動かさなければ痛みは感じなくなります。
しかし、腕を前に90°以上上げると痛みが出たり、腕を後ろに回せなくなるなどまだまだ痛みは強い状態です。
また、急性期の激しい炎症が原因となり、筋肉が引きつれ、収縮し硬くなってしまうため、肩関節の可動域が狭くなってしまいます。
これによって、腕が上がらない、動かないと感じます。
「肩関節拘縮」といって、痛みが強く腕を大きく回転させることが全くできなくなることもあります。
・融解期
回復期ともいい硬くなった肩の関節が徐々に動き出してくる時期です。
痛みもほぼなく痛める前の生活が送れますが、急性期、慢性期にケアをしないと肩の可動域が下がってしまう傾向にあります。
今回は四十肩、五十肩について書きました。
なかなか治りづらいですし、個人差もあり辛い時間が長く続く方もいらっしゃいます。
ただしっかりケアをしていかないと良くなった時に大きな差が出る事になります。
肩の痛みで困っているかた、もしくは身体の不調を抱えているかたも気軽にご連絡ご相談ください!
ふどうまえ駅前整骨院
2022.5.12
みなさんこんにちは!
寒い日があったり、暖かくなったりして変な気候ですが、体調はいかがでしょうか?
体調を崩しやすい気候だからこそしっかり栄養をとり、休息して身体を労わってあげましょう!!
又、今月はゴールデンウイークがあり、出かける機会も多いと思いますのでしっかり栄養をつけて今年のゴールデンウイークを満喫してください!
今月の旬な食材をご紹介していきます!!
【ウド・カブ・さやえんどう・シイタケ・グレープフルーツ・いさき・さわら】が旬な食材です!
この中でも『ウド・カブ』をご紹介いたします!!

☆ウド
カリウムは過剰に摂取したナトリウムを体外へと排泄し、血圧を安定させたり体内に滞った余分な水分を排泄してむくみを解消させる作用があります!
銅は血液中のヘモグロビンに鉄分を送り届ける役割を担っています。銅は多くの酵素の材料となり、体内に溜った活性酸素を除去・骨粗鬆症予防にも役立っています。
葉酸も含んでおり、身体を形作る細胞の複製には欠かせない、DNAを合成する重要な働きをになっています。
また、妊婦さんも積極的に摂取して頂きたい栄養の一つが葉酸です!
ウドは疲れにくく抵抗力を保つ、アスパラギン酸が豊富に含まれています。アスパラギン酸が不足すると疲れやすく抵抗力が弱まったりしてしまいます。
アスパラギン酸は体内でも作られますが、少ない為食材から摂取した方が良いですね!
また、アンモニアなどの有害物質を体外に排泄し神経を守る効果もあります。
ウドに含んでいる成分のジテルペンアルデヒドは血液循環を良くし、疲労回復に効果があると言われています。
ウドの成分にはクロロゲン酸という抗酸化性を示す物質を含んでおり、ガンの発生予防や日焼けによるメラニン抑制などの効果があります!

☆カブ
カブはアブラナ科の一種で旬な時期は一年の間で2回あり、3月から5月・10月から12月の2回が旬な時期になります。
春ものは柔らかい肉質が特徴的で、秋ものは甘みが強くなることが特徴的です。
カブにはアミラーゼが含まれており、アミラーゼとはでんぷんを分解する消化酵素の総称です。
唾液や膵液に含まれている成分でごはんやパンなどのでんぷん消化・吸収を促す効果があります。カブの実にはアミラーゼが豊富に含まれているので、胃もたれ・胸やけなどの症状を改善する効果があります。
イソチオシアネートも含まれていて、イソチオシアネートとは辛み成分です。
抗酸化作用があり、免疫力を高める効果や抗がん作用も期待できます。
又、胃腸を刺激して食欲を増進させれ効果や解毒作用・殺菌作用もあります。
葉の部分には豊富に含まれているβカロテンがあり強い抗酸化作用があります。
さらにビタミンAもふくんでおり、ビタミンAは目の機能・皮膚や粘膜の健康に保つ為に必要なビタミンで粘膜のダメージを回復する効果や免疫力を高める効果があります。
・肌荒れ予防にも効果が期待され、強い抗酸化作用でアンチエイジングにも効果があります。
脂溶性ビタミンのため油と一緒に摂る事で吸収率アップします。
・カブの葉には実の約4倍のビタミンCが含まれています。ビタミンCはコラーゲン合成に関わるビタミンでストレスから身体を守る働きをします。活性酸素を消去する抗酸化作用があり、動脈硬化の予防にも効果があります。
傷や炎症の治りを良くする効果もあります。
ビタミンCは水溶性ビタミンで熱に弱い性質があるので、生で食べた方が効果的に摂取できます。
・カブの葉にはカルシウムも豊富に含まれており、骨や歯を作る為には欠かせないミネラルです。体内にあるカルシウムの99%は骨と歯に存在しています。又、筋肉を動かしたり精神の興奮を抑えて安定させるなどの効果もあります。
カルシウムは吸収されにくい栄養素の一つですが、ビタミンDと一緒に摂る事で吸収率が良くなります!
このようにウドとカブには栄養豊富な成分がある為積極的に摂って楽しい日々を送れるようにしていきましょう!!
2022.5.1
みなさんこんにちは!!
4月に入りましたね!
みなさんはどうお過ごしでしょうか?
4月といえば新学期が始まる時期や、新生活がスタートさせる方も多いかと思います!
新生活をスタートさせる為にもしっかり睡眠・栄養がある食事・適度な運動を心がけている方もいない方など様々だと思います。
この睡眠・食事・運動を心がけている方はそのまま続けて頂き、出来ていない方はなるべく気を付けたいところですね!
4月の行事といえばお花見や十三参り(数え年で13歳になった子どもが健やかに成長したことを感謝し、知恵と福徳を授かる為に虚空菩薩(こくうぼさつ)にお参りする行事。)や潮干狩りなどが行事としてあります。
今回も栄養のある食材を紹介させて頂き、これらの行事などを楽しみましょう!!
4月の旬な食材は【アスパラガス・カブ・たけのこ・ぶんたん・アサリ・ハマグリ】などです!
その中でも《アスパラガス・タケノコ》を紹介していきます!!
☆アスパラガス

アスパラガスは細長い見た目で、あまり栄養がなさそうに見えがちですが、実は栄養豊富な緑黄色野菜の一種です!!
アスパラガスの中のグリーンアスパラガスをご紹介いたします。
・アスパラギン酸
アスパラガスに含まれる栄養素として有名なのが疲労回復・スタミナ増強に効果があるアミノ酸の一種のアスパラギン酸です!
アスパラギン酸は体内のエネルギー代謝を活発にする作用があり、栄養ドリンクに含まれる成分としてもおなじみです。
・ルチン
ルチンは生活習慣病予防やアンチエイジングに効果が期待できます!
ルチンはアスパラにふんだんに含まれているポリフェノールの一種です。毛細血管を強く丈夫にして血流を改善してくれるので、高血圧や動脈硬化・脳卒中・心臓疾患などの生活習慣病の予防に効果があるとされています。
又、ビタミンCの吸収を促進するので抗酸化作用も期待でき、アンチエイジングや認知症予防にも有効です。
・葉酸
アスパラにはDNAや細胞の合成に関わる葉酸もたっぷり含まれています。
葉酸はおなかの赤ちゃんの発育に必要不可欠で妊娠中の女性にとっては特に重要な栄養素のひとつです。
赤血球の造成を助ける働きもあり、貧血や動脈硬化の予防にも役立つとされています。
βカロテンや各種ビタミン
アスパラに含まれるβカロテンやβカロテンから作られるビタミンAには強力な抗酸化作用があり、ガンや糖尿病・アルツハイマー病など様々な疾患の要因となる活性酸素を除去する効果があります!
又、シミやシワなどの肌の老化を抑える働きもあるので、美肌を保つ為には欠かせない栄養素です。
このほかにもアスパラは抗酸化力が強いビタミンCやビタミンEなども豊富に含んでいます。
☆タケノコ

タケノコには様々な栄養素が含まれていますが、その中にタンパク質があります。
タンパク質の他にもカリウム・食物繊維・チロシンがあります。
・タンパク質
三大栄養素(タンパク質・糖質・脂質)のうちの一つにタンパク質があります。
その働きは筋肉や臓器の構成成分になる!など身体を作る上で重要な役割を持つ栄養素です!!
・カリウム
カリウムは身体の余分な塩分を水分と一緒に排出してくれる働きがあります。
むくみが気になる方・血圧を下げたい方には積極的に摂っられた方がオススメです!
・チロシン
タケノコに付いている白い粉は実はチロシンなのです!
チロシンはタンパク質の元となるアミノ酸の一種です。チロシンはドーパミンという神経伝達物質を合成する際に必要で幸せを感じたり、集中力を上げるなど脳を活性化させるはがあります!
・食物繊維
便通を良くする為に食物繊維を摂る事は有名ですが、タケノコには食物繊維も多く含まれています。
食物繊維には水溶性・不活性食物繊維があり、タケノコはほとんどが不活性食物繊維です!!
不活性食物繊維は水を含むと膨らみ便の量を増やす事で腸を刺激して便通を良くする働きがあります!
アスパラガスやタケノコを食べ春を感じながら元気に過ごせる身体作りをしていきましょう!!
2022.4.1
・ 40代
・ 女性
・ デスクワーク
1.発生理由
肩こりに10代のころから悩んでおり今に至る。
雨の日や仕事が忙しいと腕の方にも重ダルさや痛みが出てくる
2.受診理由
なんとかしようと決心し家から近い場所で探した
3.体の状態と施術内容
肩甲骨、頸椎のゆがみが大きく筋肉の硬結も強く出ている状態でした。
なぜ腕の方にも痛みを感じるかというと、腕の神経は首から出ているため首に異常があると腕の方にも症状が出る事があります。
今回はモルフォセラピーで骨の矯正や神経の通りを良くして、筋肉のゆるみを出すようにしました。
4.受診後の患者さんの感想
軽さがでて辛いと感じる事が減りました!
☆当院では、その方の生活背景や癖など、1人1人の不調の原因を見極めるように努めさせて頂いております。
・どこに行っても良くならない痛み
・施術してもすぐに痛みが戻ってしまう
1人1人の原因を見極めることによりこのようにお悩みの方に対しても喜んで頂いております。
不動前駅にお勤めの方。
西五反田、目黒にお住みの方。
目黒不動尊に用がある方。
どんな方でも構いませんので、気軽にお越しください。
当院は日曜日も診療しております。
気になる方はご連絡ください(^^)
2022.3.30
みなさんこんにちは!
あっという間に2022年も3月に入りましたね!
みなさんはどうお過ごしでしょうか?
3月といえばお雛祭り(桃の節句)がありますね!!
お雛祭り(桃の節句)は桃の花が咲く頃に女の子をお祝いする行事です。
女の子の健やかな成長や幸せを祈ってお祝いをします!
健やかな成長や幸せが来るように、3月の旬な食材を紹介していきます!!
3月の旬な食材は【からし菜・カリフラワー・菜の花・ワラビ・はっさく・ワカサギ・ヤリイカ・ハマグリ】などです。
その中でも《からし菜・菜の花・ワラビ》の食材をご紹介いたします。
☆からし菜

・からし菜はカリウムが豊富に含んでいます!
カリウムにはナトリウム(塩分)を排泄する役割があり、高血圧に効果があります。又、長時間の運動による筋肉の痙攣などを防ぐ働きもあります。
カリウム以外にもカルシウム・マグネシウム・リン・鉄分などミネラルも豊富です。
カルシウム・マグネシウム・リン・鉄分は骨を生成するのにとても大切です。
βカロテンや葉酸も豊富で、βカロテンは抗発がん作用や動脈硬化の予防が期待できます。βカロテンは体内でビタミンAに変換され、髪の健康維持・視力維持・粘膜や皮膚の健康維持・喉や肺など呼吸器系統を守る働きがあるとされています!
又からし菜は葉酸も含んでいる為、妊婦さんにはとても大切になってきます!
☆菜の花

菜の花はアブラナ科アブラナ属の全ての花のことをいいます。菜の花は菜花(なばな)とスーパーで目にすることがあります。
菜花と菜の花は同じ事になります。菜花はアブラナ科アブラナ属の野菜の総称になるので、キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー・ザーサイなども菜花となります。
野菜としてスーパーなどで出回っているのが、菜花(なばな)です。菜花は一般的にはアブラナの若い茎とつぼみをさします。
菜花は花を咲かせる前なので、植物が生長する為に必要な栄養分をたくさん含んでいるので栄養豊富です。
菜花を辛いと感じる方も多いでしょう!!この辛味はイソチオシアネートという成分によるもので強い抗酸化作用があります!
このイソチオシアネートは免疫力を高め、がん予防の効果も期待できます!
又菜花はビタミンCも豊富で100gあたり130mgも含まれています。
ビタミンCにも抗酸化作用や免疫力アップの効果が期待でき、血管を強化したり美肌を育成したりする効果も期待できます。
造血作用がある葉酸もたくさん含まれているので貧血気味の方や妊婦さんにもオススメです!!
それ以外にも鉄・カルシウム・カリウムなども含まれています。
☆ワラビ

ワラビは抗酸化力が強いビタミンEが含んでいます。ビタミンEには活性酸素を抑え体内の不飽和脂肪酸の酸化を防ぐ働きがあるので動脈硬化・心筋梗塞などの生活習慣病の予防に役立っています。
※ワラビには強い毒性があります!!
ワラビは十分に灰汁抜き(あく抜き)をしないと強い毒性のある成分もあります。灰汁抜きをしないで大量に摂取してしまうと、大量出血症状を起こしさらに骨髄を壊して死に至ることもあるようです。灰汁をしっかり取り除いておけば問題はないので、しっかりと処理をするようにしましょう!!
◎ワラビの灰汁(アク抜き)のやり方
・鍋にたっぷりのお湯を沸かし(2リットル程)、沸騰したら重曹を入れる。
・すぐにワラビを投入し、10秒程経過したら火を止め、そのまま自然に冷えるまで放置しておく。
・しっかり冷めたら灰汁(アク)が抜けているのできれいな水でゆすいで大きめの密閉容器等に水に浸した状態で入れ、冷蔵庫で保管します!!
もし重曹がない場合には、沸騰した水で茹でてそれを冷水にさらしておけばかなりアクが抜けています。
冷蔵庫での保存で時々水を替えておけば5日程はもちます。
春が近づいてきたので、山菜採りなども良さそうですね!!栄養をしっかり摂って健康な身体作りをしていきましょう!!
2022.3.1
こんにちは!
今年もあっという間に2月になりましたね。
寒い日が続きますが、皆さま体調はいかがでしょうか?
2月と言えば、節分や立春などがありますね!
節分で豆まきをして、鬼(COVID-19)を外に追いやりたいですね。
コロナウイルスを退治するためにも免疫力を高めていき、コロナウイルスだけではなくインフルエンザウイルスやノロウイルスに負けない身体づくりをしていきましょう!!
免疫力を付けるためにも2月の旬な食材をご紹介していきます!!
2月の旬な食材は【芽キャベツ・明日葉・春菊・カブ・キウイフルーツ・デコポン・赤貝・ブリ・白魚】などが旬な食材になります。
その中でも、≪芽キャベツ・春菊・白魚≫の栄養をご紹介いたします。
☆芽キャベツ

・芽キャベツには一般的なキャベツに比べてほとんどの栄養成分においてたくさん含まれています。
ビタミンCが豊富。(風邪の予防や疲労回復・肌荒れなどに効果があると言われているビタミンCの栄養素がキャベツは41mgに対し160mgと約4倍の栄養素があります。
ビタミンKが豊富。血液凝固促進や骨の形成に関与するビタミンKが芽キャベツの方がキャベツよりも約2倍の栄養素があります。
その他の芽キャベツの栄養素はβカロテン(抗酸化作用)・ルテイン(抗酸化作用)・ジアスターゼ(でんぷん分解酵素)
・美味しい芽キャベツの選び方
色が鮮やかで大きさや形が揃っている物が一番良いです!!
芽キャベツは緑色が濃く、固くしっかりと巻いていそうな物を選びます。手に持った時になるべく重く感じるものが良いです。
黄色みを帯びたものは鮮度が落ちているので避けた方が良いです。
・芽キャベツの保存方法
①芽キャベツは洗わずに、乾燥しないよう通気性のあるビニールパックなどに入れ冷蔵庫で保存します。
そのようにすることで生で1週間ほど持ちます。ですが、なるべく早めに使うようにした方が良いです。
②芽キャベツを冷凍保存する場合はさっと固めに茹でて、小分けしたものを冷凍します。解凍は自然解凍が好ましいです。
☆春菊

春菊は緑黄色野菜の中でトップクラスの栄養素が含まれています。
抗酸化作用がありβカロテン・ビタミンCが多く、骨の形成に必要なカルシウム、貧血予防に役立つ鉄分、妊娠初期の女性にとても大切な葉酸などが多く含まれています。
春菊には独特な香りがありますが、この香り成分にはべリルアルデヒドという成分があります。このべリルアルデヒドには免疫力を高めたり胃腸の調子を整え、咳を鎮める効果もあります。
このクセがある香りが苦手。という方もいると思いますが、栄養素が高い野菜なのでぜひ食べて頂きたいですね。
☆白魚
![白魚 写真素材 [ 4786418 ] - フォトライブラリー photolibrary](https://www.photolibrary.jp/mhd7/img503/450-20161215213725303818.jpg)
白魚の栄養素はドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)などが含まれています。
ドコサヘキサエン酸(DHA)には体内の免疫反応の調整や脂肪燃焼の促進、血管壁の収縮、血小板の凝集にかかわるなど様々な働きがあります。
アレルギー疾患・高血圧・動脈硬化・脂質異常症・脳卒中・皮膚炎の予防と改善にも効果が期待できます。
エイコサペンタエン酸(EPA)にも免疫反応の調整やアレルギー疾患・高血圧・動脈硬化・脂質異常症・脳卒中・心筋梗塞・炎症性・血栓症の症状の予防と改善に効果が期待されます。
この2つの栄養素以外にもカルシウム・マグネシウム・リンなどもあり、骨の形成にも関係してきます。
又、レチノールが多くあります。レチノールを取り入れる事により体内でビタミンAに変わります。
このレチノールは活性酸素を抑え動脈硬化・心筋梗塞などの生活習慣病対策となるほか、皮膚や粘膜の細胞を正常に保ち免疫力も高まります!!
・白魚の鮮度の見分け方
白魚は生きている時は半透明で死後時間が経つにつれて白くなっていきます。購入する際にはできるだけ透明感がある白魚を選んだ方が新鮮です!
2月も始まりましたが、まだまだ寒さが続くので、栄養がある食材を食べて元気な身体づくりをしていきましょう!!
2022.2.1

クレジットーカードでのお支払いは、自費診療と物販製品のみご利用可能です。
保険診療の一部負担金にはご利用いただけません。